駒ヶ根市自治組織の在り方検討会

少子高齢化が進み、さまざまな事情や価値観の違いから、それぞれの思いのすれ違いが生まれてきています。そのような中、ウィズコロナ時代を迎え、人と人とのつながりや地域社会、コミュニティの在り方が問われています。
この時代の大きな節目に、新しい時代にふさわしい駒ヶ根市のコミュニティの形を作り上げるべく、駒ヶ根市自治組織の在り方検討会を開催します。区からの推薦や、自治組織未加入の中から公募の方、共通の課題がある団体、子育て世代、移住者、学生、企業からの推薦などさまざまな立場の委員により構成し、令和5年12月21日から2年程をかけて「駒ヶ根モデル」の創出を目指し検討を進めます。
第1回会議 市長あいさつ (PDFファイル: 142.2KB)
提言書の提出(令和8年1月26日)

これまで約2年間をかけて検討していただいた自治組織の在り方に関する提言書を市長に提出していただきました。当日は森岡強座長と岡田敦子副座長から、提言書が市長に手渡されました。
自治組織の在り方に関する提言書 (PDFファイル: 1.2MB)
第11回会議(令和8年1月13日市役所第5会議室)
第10回会議(令和7年11月20日市役所大会議室)
第9回会議(令和7年10月1日市役所大会議室)
【資料0】提言までのロードマップと次年度の展開 (Wordファイル: 35.3KB)
【資料1】自治会フォーラムアンケート回答 (Wordファイル: 43.0KB)
【資料2】自治会フォーラムグループ発表掲示より (Wordファイル: 44.9KB)
【資料3】自治会フォーラム会議録 (Wordファイル: 50.7KB)
【資料4】自治会フォーラム会議録【要約版】 (Wordファイル: 37.8KB)
【資料5】自治組織に関する提言書草案ver.2箇条書き (Wordファイル: 25.1KB)
【資料6】提言書構成案【素案】 (Wordファイル: 32.3KB)
提言書ver.70424_1自治組織向け (Wordファイル: 3.1MB)
提言書ver.70424_2市役所向け (Wordファイル: 3.1MB)
駒ヶ根市自治会フォーラム(令和7年8月3日 赤穂公民館ホール)
令和7年8月3日(日曜日)午後1時30分から自治会フォーラムを開催し、80名に参加いただきました。
駒ヶ根市自治会フォーラム会議録 (Wordファイル: 48.0KB)

自治会フォーラム次第
市長あいさつ
自治会フォーラムの進め方
これまでの経過説明:合理性から共創へ 副座長:岡田敦子さん
パネルディスカッション趣旨説明(白戸教授)
■林英之さん1.「若い世代の関心と事務局体制の必要性」
■加治木今さん1.「世代交代とお金の在り方を問う」
■森岡強さん1.「“顔が浮かぶ”関係の価値と将来予測」
■倉田正清さん1.「委員のあり方と公共施設の維持課題」
■林英之さん2.「消防団と楽しさから始まる地域づくり」
■加治木今さん2.「“地域の教科書”と共に育む小さな集い」
■森岡強さん2.「人選の負担と将来への不安」
■倉田正清さん2.「外国人も含む“顔の見える”関係構築を」
■白戸教授まとめ「“自分の地域”から始める行動を」
グループ・ディスカッションの進め方【事務局】
グループ1:「自治会は必要ない」のか。改革より現実的な改善へ
グループ2:自治会が抱える課題の多さと不満、見直しの必要性
グループ3:多様性への配慮と教科書づくりの重要性
グループ4:人とのつながりの再構築と情報の見える化
グループ5:世代交代と事業の見直しの必要性
グループ6:組織のスリム化と福祉対応の両立
グループ7:防災を軸にした自治組織の存在意義の再確認
グループ8:具体的な実行段階への転換を提案
グループ9:行政依存の見直しと明確なメリットの提示
グループ10:高齢化と担い手不足への具体策を模索
その他:自治会の必要性を市として示すべき
講評:白戸洋教授
伊藤市長の期待表明
【要旨】パネルディスカッション、グループ発表 (Wordファイル: 35.4KB)
グループ発表掲示物の内容【箇条書き】 (Wordファイル: 42.3KB)
自治会フォーラムにおけるアンケートへの意見 (Wordファイル: 0B)
自治会フォーラムプログラム (PDFファイル: 920.7KB)
自治組織の在り方検討会の経過について【スライド】 (PDFファイル: 1.5MB)
自治組織の在り方検討会の経過について【読み原稿】 (PDFファイル: 133.8KB)
駒ヶ根市自治会フォーラム
駒ヶ根市自治会フォーラムを次のとおり開催します。多くの皆様のご参加をお願いします。
| 日時 | 8月3日(日曜日)午後1時30分〜午後3時30分(午後1時開場) |
|---|---|
| 場所 | |
| 入場 |
入場は無料ですが、事前申し込みをお願いします。 (注意)オンライン視聴の場合申し込みは不要で、定員はありません。 |
|
申込期間 |
申込期間 6月25日(水曜日)〜7月29日(火曜日) 予定数に達し次第終了 |
|
申し込み方法 |
1.ウェブフォームからの申し込み ウェブフォームからお申し込みください。 |
|
2.Eメールでお申し込み メール本文に必要事項を記入し、以下メールアドレス宛に送信してください。 メールアドレス gyosei@city.komagane.lg.jp 件名に「駒ヶ根市自治会フォーラム申し込み」と記載してください。本文に参加される方全員の「お名前・ふりがな・住所・電話番号」を記載してください。 |
|
|
3.ファクシミリで申し込み 必要事項を記載し以下ファククシミリ番号へ送信してください。 ファクシミリ番号 0265-83-4348 参加される方全員の「お名前・ふりがな・住所・電話番号」を記載してください。 |
|
| 対象 | 自治会活動や地域づくりに関心がある市民 |
| 内容 |
1.パネルディスカッション 「在り方検討会のグループワーク」防災、ゴミ・支え合い・子育て、若者に選ばれる地域づくり」 コーディネーター 松本大学 白戸洋教授 2.みんなでグループワーク グループに分かれて、パネルディスカッションの内容について、参加者の皆さんの意見を出し合っていただきます。 3.参加型展示イベント 「ジチの木」 テーマ「こんな自治会なら関わりたい」 来場者の皆さんに、自治会のミライについてのアイディアや想いを「葉っぱ」や「実」に見立てて木に貼る参加型展示です。 |
| 開催 |
|
駒ヶ根市自治会フォーラムチラシ (PDFファイル: 1.5MB)
第8回会議(令和7年4月24日 市役所大会議室)

提言書の事務局案(会議前に事前送付し意見聴取)や、夏に行われるフォーラムディスカッションの内容について検討します。また、今後検討会が実践する取り組みの話し合いも行います。
会議資料:提言書草案_市役所向け (Wordファイル: 3.1MB)
会議資料:提言書草案_区や自治会など自治組織向け (Wordファイル: 3.1MB)
会議資料:自治会フォーラムディスカッション企画案 (Wordファイル: 30.9KB)
検討会委員を公募します
市民の皆さんの幅広い意見を行政に反映させていくため、区や自治会等の自治組織の課題の議論を行う自治組織の在り方検討会の委員を公募します。
| 募集する委員 | 学生の方 若干名 |
|---|---|
| 応募期限 | 令和7年3月14日(金曜日)必着(郵送の場合は消印有効) |
| 応募資格 |
学生(学校教育法に定める大学、短期大学、高等専門学校の学生)で次の条件をすべて満たす方
|
| 任期 | 検討会委員の任期(令和7年12月頃までを予定) |
| 応募方法 |
|
| 選考方法 |
|
| 応募先・問合せ先 | 総務課 自治組織創生室 |
第7回会議(令和7年1月24日 市役所大会議室)

これまで議論してきた内容を、検討会として地域に説明する方法についてグループごと検討しました。
(1)防災をどうするか〜
「地域の教科書」を作成し、区や自治会などの情報の見える化を図ったり、ホームページを設けるなどして、情報発信する。
(2)コミュニティのシステムをどうするか〜
- QRコードでホームページへ誘導する。
- ゴミのシステムについて、参加型にすることで地域の一体感を醸成する。
- 子育てイベントなど情報発信をホームペジで行う。
(3)若者に選ばれる地域づくり〜
- 移住・定住してもらえる環境づくり、コミュニケーションの場づくり
- 「楽しい」「うれしい」と思える仕掛け
- 野菜を配る野菜の収穫イベント野菜を持ち寄ってイベント
- 虫取り・魚とりイベント
- そば打ちイベントを通して若者とコミュニケーション
- 信頼関係を作るところから始めて、自治会に巻き込む雰囲気づくり
- 自治会へ伝えるのは、提案・アイディアを 押し付けにならないように
グループ1防災と自治組織_伝える方法 (PDFファイル: 219.1KB)
グループ2ゴミ福祉子育てと自治組織_伝える方法 (PDFファイル: 214.2KB)
グループ3移住・定住で若者に選ばれる自治組織_伝える方法 (PDFファイル: 813.9KB)
第6回会議(令和6年10月23日 保健センター大会議室)

グループワークのテーマは第5回と同じテーマ「グループ1 防災と自治組織」、「グループ2 子育て・ゴミ・福祉と自治組織」、「グループ3 若ものに移住定住してもらえる自治組織」について話し合いました。サブテーマを「自治組織がなくなったらどうするか」として、視点を変えて議論を掘り下げました。
グループ1防災と自治組織_自治組織がなくなったらどうするか (PDFファイル: 115.0KB)
グループ2ゴミ福祉子育てと自治組織_自治組織がなくなったらどうするか (PDFファイル: 123.0KB)
グループ3移住定住先として若者に選ばれる自治組織_自治組織がなくなったらどうするか (PDFファイル: 336.3KB)
先進地視察(令和6年8月27日 県生涯学習推進センター 飯田市の取り組み事例)
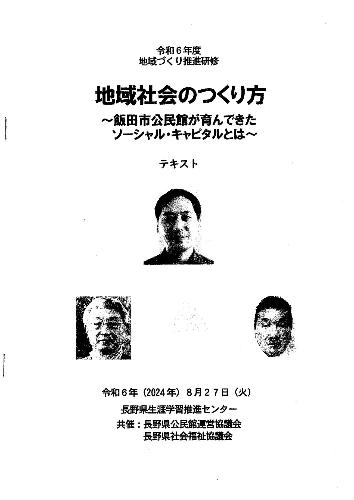
委員の情報収集の一環として先進地視察を行いました。8月27日(火曜日)に長野県生涯学習推進センターで行われた研修会に委員5名が参加しました。「地域社会のつくり方 公民館が育むソーシャル・キャピタル」と題し、日本女子大学准教授の荻野亮吾氏の講義をお聞きしました。公民館・地域づくりの学術的な位置づけや定義について、長く飯田市に入られている見地からのお話でした。その後、元飯田市公民館副館長の木下巨一氏、飯田市竜丘地区で公民館の文化スタッフを務められた加藤守孝氏の鼎談「飯田市公民館は、どのようにソーシャル・キャピタルを育んできたか」をお聞きしました。
第5回会議(令和6年7月17日 市役所大会議室)

前回の議論の中から、話し合いたいテーマを募り、希望するテーマに分かれてグループワークを行いました。グループワークのテーマは、(1)防災を通じて、(2)ゴミ、子育て、福祉などのシステムについて、(3)若い人に移住・定住してもらうには、のそれぞれに関わり、自治組織をどうすべきかを議論しました。
グループワーク結果発表1_防災を通じて自治組織をどうすべきか (PDFファイル: 110.9KB)
グループワーク結果発表2_ゴミ、子育て、福祉などのシステムについて自治組織をどうすべきか (PDFファイル: 178.0KB)
グループワーク結果発表3_若い人に移住・定住してもらうには自治組織をどうすべきか (PDFファイル: 183.3KB)
第5回会議録_一部要約 (PDFファイル: 562.7KB)
第4回会議(令和6年4月24日 市役所大会議室)

第3回に引き続き2月に行った白戸先生の講演会の感想をテーマに、2回目のグループワークを行いました。議論をさらに深め、次回検討会で話し合いたいテーマや、議論の進め方に対する意見を出し合いました。いくつかのアイディアやキーワードが出てきていて、今後のグループワークで具体的に話し合う準備ができてきました。
第4回グループワーク結果発表A (PDFファイル: 355.2KB)
第4回グループワーク結果発表B (PDFファイル: 215.0KB)
第4回グループワーク結果発表C (PDFファイル: 445.7KB)
第4回グループワーク結果発表D (PDFファイル: 355.3KB)
第3回会議(令和6年3月14日 市役所南庁舎大会議室)

前回の白戸教授による講演会の内容や自治組織に関することをテーマに、グループワークを行いました。AからDまでの4グループに分かれ、進行や記録、タイムキーパー、発表など委員の運営により議論を進めました。まとめに4つのグループから結果の発表を行い、全体で共有をしました。
第3回グループワーク結果発表A (PDFファイル: 2.2MB)
第3回グループワーク結果発表B (PDFファイル: 403.5KB)
第3回グループワーク結果発表C (PDFファイル: 441.2KB)
第3回グループワーク結果発表D (PDFファイル: 1.7MB)
第2回会議(令和6年2月14日 市役所南庁舎大会議室)

本検討会アドバイザーの松本大学白戸洋教授を講師にお迎えし、基調講演会を行いました。
自治組織の基本的なことについて、ユーモアを交えながら、自身の経験を軸に楽しく講演いただきました。白戸教授は、「自治組織は農業とともに地域の中に成り立ち、時代ごとにその機能と役割が変化してきた」と説明。そして現在、再び「地域」が必要とされていると話し、日頃から周りの人とコミュニケーションを取り合うことの大切さを呼び掛けました
検討会委員20名のほか、ご応募いただいた一般聴講者42名の皆さんが、和やかな中にも熱心に聴講していました。
基調講演「自治組織役員のゆううつ」レジュメ (PDFファイル: 88.7KB)
【資料】⽩⼾先⽣の講演会から考える在り⽅検討会の整理(第2回講演会のイメージ図) (PDFファイル: 142.2KB)
講演会チラシ 講師 松本大学総合経営学部教授 白戸洋先生 (PDFファイル: 340.5KB)
第1回会議(令和5年12月21日 市役所大会議室)

第1回会議では、委嘱書を交付し、市長から委員の皆様にあいさつがありました。事務局から市民アンケート、自治組織へのアンケートと分析結果について説明があった後、アイスブレイクとして各委員から自己紹介も兼ねて自治組織にについて一言ずつ発言していただきました。
駒ヶ根市自治組織の在り方検討会の構成 (PDFファイル: 337.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 自治組織創生室
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線211
ファックス 0265-83-4348
お問い合わせフォームはこちら
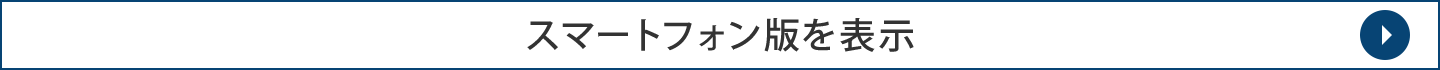








 総合トップ
総合トップ 組織から探す
組織から探す 相談窓口
相談窓口 お問い合わせ
お問い合わせ 行政サイト
行政サイト 移住定住サイト
移住定住サイト 子育てサイト
子育てサイト 観光協会
観光協会
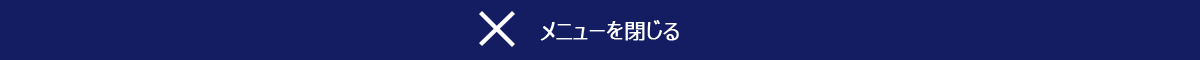


更新日:2026年01月26日