国民健康保険税の概要
税額の算定方法
国民健康保険税は
- 所得割 その世帯の所得に応じて算定
- 均等割 加入者一人当たりいくらとして算定
- 平等割 一世帯当たりいくらとして算定
の3つの合計で、一世帯当たりの年間保険税を算出します。
令和7年度 駒ヶ根市の税率
令和7年度の税制改正により、以下が変更されています。
【課税限度額の引き上げ】
これまで医療分の課税限度額は65万円でしたが、66万円になります。
後期高齢者支援金分の課税限度額は24万円でしたが、26万円になります。
介護分の課税限度額は17万円で変更はありませんので、最大で109万円の課税額となります。
【減額の対象となる所得基準の見直し】
5割軽減と2割軽減が適用される所得基準の計算が以下のように見直されました。
- 5割軽減:被保険者数に乗ずる金額が 29 万5千円 から 30万5千円に変更
- 2割軽減:被保険者数に乗ずる金額が 54万5千円から 56万円に変更
| 所得割 | 均等割 | 平等割 | 賦課限度額 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 6.69% | 20,200円 | 21,300円 | 66万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.79% | 8,800円 | 7,700円 | 26万円 |
| 介護納付金分 | 2.27% | 8,700円 | 7,200円 | 17万円 |
なお、具体的な計算方法や納税通知書の見方は、次のファイルをご覧ください。
国民健康保険税の計算方法 (PDFファイル: 150.0KB)
令和7年度納税通知書の見方 (PDFファイル: 1.4MB)
| 7割軽減される場合 |
世帯主と被保険者の令和6年中の合計所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)で計算した額以下の世帯 |
|---|---|
| 5割軽減される場合 |
世帯主と被保険者の令和6年中の合計所得金額が43万円以上あり、43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)で計算した額以下の世帯 |
| 2割軽減される場合 |
世帯主と被保険者の令和6年中の合計所得金額が43万円以上あり、上記(5割軽減)に該当しない世帯で、43万円+56万円 ×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)で計算した額以下の世帯 |
(注意1)給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金の支給を受ける者のことをいいます
(注意2)軽減税率の適用を受けるのは【均等割額と平等割額】のみです
産前産後期間の所得割と均等割の減免
子育て世代の負担軽減や育児支援のため、令和5年11月以降に出産される国民健康保険被保険者の方を対象に、所得割と均等割の減免をしています。減免を受けるためには届け出が必要です。
出産前後の期間(単胎の方は出産予定月の先月から4カ月間、多胎の方は出産予定月の3カ月前から6カ月間)の対象者の国民健康保険税から、所得割と均等割を減免することができます。
出産予定日の6カ月前から届け出を受け付けています。出産後の届け出も可能です。詳しい内容や、届出に必要な書類については以下リンク先のページをご確認ください。
未就学児の均等割5割軽減
令和4年度から、子育て世帯の負担軽減を図るため、小学校入学前の子どもの均等割を5割軽減しています。
この軽減には届出は不要です。6月中旬頃に届く国民健康保険税納税通知書でご確認ください。
なお、低所得者軽減に該当する方は、低所得者軽減適用後の均等割をさらに5割軽減します。課税限度額の適用については、未就学児の軽減を適用して保険税の算定をしてから課税限度額を適用します。
後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減
75歳以上の人は後期高齢者医療保険に加入することとなっています。
この後期高齢者医療保険に加入することによって、国民健康保険税とあわせて世帯としての負担額が急激に増えることがないように、一定期間の経過措置として軽減や減免を受けることができます。経過措置としての軽減などについては、次のとおりです。
後期高齢者医療保険に移行後、引き続き国民健康保険に加入する方がいる場合
後期高齢者医療保険に移行する75歳以上の人がいる国民健康保険加入世帯で、75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入する場合、税額を軽減します。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 所得が低い世帯の軽減 | 軽減を受けている世帯では、世帯構成や所得が変わらなければ、従前と同様の軽減を受けることができます。 |
| 平等割(一世帯当たりで賦課される分)の軽減 | 国民健康保険の加入者が1人だけになってしまう世帯については、5年間は、平等割が半額になり、6年目から8年目は3/4になります。 |
(注意)上記は手続の必要はありません。
被用者保険の被扶養者だった方が国民健康保険に加入する場合
75歳以上の人が、会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行することで、その被扶養者だった65歳以上75歳未満の人(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合、税額を軽減します。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 旧被扶養者の軽減【申請による軽減】 |
1.所得割と資産割は免除されます。 2.均等割は半額になります。(最長2年間) 3.旧被扶養者のみの世帯は、平等割も半額になります。 (最長2年間) |
(注意1)上記は申請が必要になります。
(注意2)申請は、国民健康保険に加入する届け出をしていただく際に、市民課の窓口へ併せて申請書を提出していただきます。
(注意3)令和元年度の課税から、均等割、平等割の減額を、資格取得日の属する月以降2年間と限定することとなりました。
(注意4)平成29年4月以前から減免を受けている方は、平成30年度で、均等割、平等割の減額が終了となりました。なお、所得割、資産割につきましては、引き続き免除となります。
非自発的失業者に対する税額の軽減
倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方(非自発的失業者)に対して税額を軽減します。
軽減の内容
平成22年度分以降の保険税の算定に当たり、雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などで離職した人)または特定理由離職者(雇い止めなどにより離職した人)として、基本手当の受給資格を受けている国保被保険者が世帯内にいる場合、申請により、その人の前年の給与所得を30/100とみなして課税します。
なお、65歳以上の人は対象となりません。
軽減の対象となる国民健康保険の加入期間
平成22年4月1日以降の期間で、離職日の翌日からその翌年度末までの期間
申請方法
申請書を提出していただく必要があります。次の物を持って、市民課窓口にて手続きをしてください。
- 雇用保険受給者証等
- 印鑑
刑事施設等に収容されている方に対する減免
減免の内容
刑事施設等の被収容者、被収容者であった方に対し、申請があった際には、本人に係る国民健康保険税を減免します。
対象期間
国民健康保険法第59条第1号・第2号に該当する月から該当しなくなった月の前月まで
申請方法
申請書を提出していただく必要があります。次のものを持って、市民課窓口にて手続きをしてください。
- 収容の事実を証明する書類(留置証明書、在所証明書等)
- 印鑑
国民健康保険税を滞納すると
滞納すると市税の滞納と同じように差し押さえなどの滞納処分や、次のような処分が行われます。
すぐにお支払いが難しい場合には、税務課へご相談ください。状況をお伺いした上で、分割納付など、可能な納付方法を検討します。
督促状の送付
納期限を過ぎても保険料が未納の場合、督促状が送付されます。
延滞金が徴収される場合がありますので、早めに納めましょう。
医療費が全額自己負担となる「特別療養費」の適用
督促状送付後も未納が続く場合、一時的に医療費が全額自己負担となる場合があります。対象となる方へは事前にその旨を通知します。
窓口(市民課国保医療係)にて申請することで本来の負担割合に応じた特別療養費の給付を受けることができますが、国保税が未納の場合、未納分へ給付金が充当される場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 市民税係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348
お問い合わせフォームはこちら
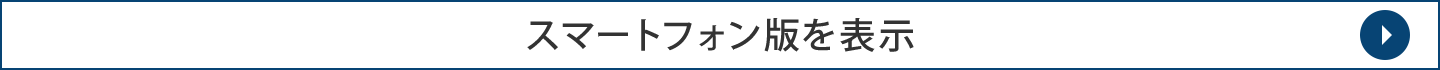








 総合トップ
総合トップ 組織から探す
組織から探す 相談窓口
相談窓口 お問い合わせ
お問い合わせ 行政サイト
行政サイト 移住定住サイト
移住定住サイト 子育てサイト
子育てサイト 観光協会
観光協会
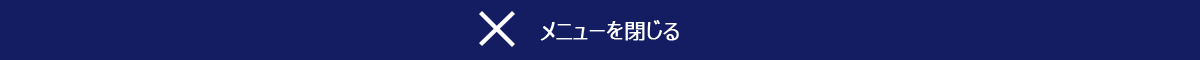

更新日:2023年05月09日