市長施政方針
施政方針とは、市長が各年度において、市政運営の基本方針や主な施策の方向性を示すものです。
令和7年度施政方針(令和7年2月20日)
ともに創ろう
“誰もが自由闊達にいきいきと活躍する広場のようなまち”駒ヶ根
1.【はじめに】
本日、令和7年第2回市議会の開会にあたり、令和7年度予算案を始め、市政の重要な議案の提案説明に先立ちまして、市政運営に対する私の所信の一端を申し上げます。
今年正月、毎日、朝日、日本経済の新聞各紙が、新年企画で「民主主義」をそろって取り上げました。新年企画は、新聞社が、その年に最も訴えたいテーマを取り上げるものです。私は長年、記者として働きましたが、これだけ多くの社が同じテーマに取り組んだことはあまり記憶にありません。それだけ、民主主義をとりまく危機感が高まっていることを示しているのではないかと考えます。
その背景には、世界各国で起きている、ポピュリストの台頭があります。象徴は再び就任した、米国のトランプ大統領でしょう。メキシコやカナダなどに関税引き上げを通告し、個別に交渉を行うやり方は、戦後の国際社会が、国の規模にかかわらず、共通で公平な枠組みをつくろうと築いてきた、多角的貿易交渉のルールから外れているとの批判があります。しかし、米国内では多くの支持者が歓声を送っています。欧州でも、多くの国で移民排斥や自国第一を訴える勢力が支持を集めつつあります。
米国の政治学者である、マイケル・サンデル氏とフランスの経済学者であります、トマ・ピケティ氏が昨年5月行った、対談をまとめた「平等について、いま話したいこと」が最近、出版されました。1980年代以降、グローバリゼーションや金融化、能力主義を柱とする、新自由主義の広がりによって、人々の間に大きな格差が生まれてしまったと指摘します。サンデル氏は、上位に立った人たちは、自分の成功は自分の手柄であり能力の証しだとして、機会さえ平等であれば、勝者は勝利に値するのだという、一見すれば魅力的な能力主義をたたえていると提起します。しかし、そこには2つの問題があるというのです。ひとつは、完全な機会の平等は実現していないこと。もう一つは、その機会の平等が実現したとしても、共通善がむしばまれていることです。共通善がむしばまれているとは、その人の成功は、幸運や恵まれた環境に助けられたり、ほかの人たちの支えのおかげだったりすることを忘れてしまうことだといいます。
サンデル氏やピケティ氏は、こうした社会課題を放置したまま、働く人たちに対して、もっと努力せよ、さらに能力を磨けということは、その人たちの尊厳を無視したエリート主義ではないか、と警告します。その結果、人々から生まれた反発をすくいあげ、攻撃の矛先として、移民らを敵に仕立て上げ、排外主義を柱とした主張に駆り立てているのが、右派を中心としたポピュリストたちだと提起します。そして、こうした主張は人々を分断し、社会を不安定化していくというのです。
危機を乗り越えるために、サンデル氏は家族から地域、国家へと続く共同体において失われてしまった、人々の帰属意識や社会的な調和を感じられるよう、自治のプロジェクトを活性化しなくてはならないと訴えています。公園や公民館など、多様な人々が混ざりあう、公の場を再構築し、同じ社会に生きる市民であることを確認する必要があるというのです。こうした取り組みを重ねることで、エリートを批判し、あたかも人々の代弁者であるかのように装う、ポピュリストに対峙しようと呼びかけています。
民主主義は手間がかかり、運用を間違えればもろく崩れやすい制度であります。しかし、これに代わる制度が見当たらない以上、大事に守っていかなくてはならないと考えます。サンデル氏の指摘は、駒ヶ根市にとっても重く受け止めなくてはなりません。私は就任以来、人々がさまざまな壁や障害を越えて、思いを広げ、活動に取り組むことができる、広場のようなまちを目指すと申し上げてきました。まさに、時代の大きな節目に当たり、あらためて、まちづくりに取り組む覚悟を固めています。
2.【令和7年度当初予算案の概要】
それでは、今定例会に提案します、新年度予算について申し上げます。
令和7年度は第5次総合計画の終盤となる4年目の年となります。総合計画の中間評価を踏まえ、目標年となる8年度に向けて、「5つの基本目標」「6つの重点プロジェクト」の各施策の目標達成にスピード感をもって取り組んでまいります。
各施策の進捗状況の検証から見えてきた課題の解決や市民サービスの利便性向上に努め、時代にマッチしたふさわしいまちづくりを進める事業へ予算配分し、「新たな時代をともに拓く予算」として編成しました。
また、足元の物価高騰による市民生活や事業者の経済活動への影響に対し、国の経済対策にあわせて、令和6年度補正予算と7年度当初予算を一体的に編成することで、切れ目のない迅速な取り組みを進めてまいります。
それでは、当初予算の概要を申し上げます。
一般会計の総額は178億4,000万円で、前年度当初予算と比べて、15億4,000万円、9.4%と大幅に増加しました。過去最大規模であった前年度を大きく上回っています。特別会計・企業会計は、104億3,085万円で1億8,664万円、1.8%減少しました。この結果、令和7年度の予算総額は282億7,085万円で、前年度当初予算と比べて13億5,336万円、5.0%の増加となりました。
3.【令和7年度の主要施策】
次に、主要な施策について、第5次総合計画に沿って順次説明します。まず、6つの重点プロジェクトについてであります。
1【重点プロジェクト】
(1)【少子化対策・子育て支援プロジェクト】
はじめに、「少子化対策・子育て支援プロジェクト」であります。第1期、第2期と取り組んでいる「子育て全力応援」により、さまざまな施策を進めてまいりました。引き続き、安心して子どもを産み育てやすい環境づくりを目指します。
(結婚、妊娠、出産の希望支援)
まず、結婚、妊娠、出産の支援であります。
結婚相談所では引き続き、相談事業や出会いイベントなどのサポート事業を通じて、結婚を希望する皆さんに寄り添った取り組みを継続して行ってまいります。
また、結婚新生活支援事業では、結婚生活スタート時の住居費や引っ越し費用、家電購入費などの補助により、若い世代の結婚の経済的な後押しを行います。
国の事業である「出産・子育て応援交付金」を活用し、引き続き「伴走型相談支援体制」を確保するとともに、妊娠時と出産時には応援ギフトをお贈りします。
(成長過程に応じた子育て支援)
次に、成長過程に応じた子育て支援であります。
ファミリーサポートセンター事業や子育て短期支援事業の拡充、保育士人材確保事業や保育補助員の導入による保育職場の環境整備を進め、必要なときに安心して子どもを預けられる体制と環境の確保に努めてまいります。
また、子どもの未来応援事業として、学習支援や生活支援・相談など、子どもたちの居場所づくりに取り組むNPO法人や市民団体などへの支援を引き続き行ってまいります。
子育て参画促進事業では、子育てが楽しく、生きがいを感じられる環境づくりのため、企業などと連携しセミナー開催などを実施してまいります。
公園の遊具等の更新を引き続き実施し、子どもたちが安心・安全に遊べる環境整備を進めます。
(移住・定住支援)
若者の移住定住に向けた経済的支援であります、奨学金の返還補助につきましては、令和7年度から補助額を増額し、さらなる拡充を図ります。
(2)【共生社会づくりプロジェクト】
次に、2つ目の重点プロジェクト、共生社会づくりであります。世代や分野を超えて、誰もが生きがいと暮らしやすさを感じられる「地域共生社会」の実現に向け基盤づくりを推進してまいります。
(包括的支援体制の整備)
少子高齢化・人口減少が進展し、暮らしを取り巻く課題への対応は、これまでの仕組みだけでは難しくなっています。複合化・複雑化した福祉の支援ニーズに対応する包括的な支援体制の充実を図ってまいります。
また、困りごとを抱えている人や家族を孤立させず、継続的に関わる伴走型支援によって、経済的・日常的・社会的な自立を支援するとともに、関係機関との横断的な連携を強化してまいります。
(地域活動の担い手の育成)
また、共生社会を構築するためには、「支え手」「受け手」という関係を超えて住民の皆さんや、地域の多様な主体が「我が事」として参画することが重要です。市民の皆さんの地域福祉への意識を醸成し、ボランティア活動への啓発や住民主体による支え合い体制の充実を図り、共感やつながりをベースにした「人財」の育成を図ってまいります。
(3)【生涯活躍のまちづくりを軸とした中心市街地(まちなか)再構築プロジェクト】
次に、3つ目のプロジェクト、「生涯活躍のまちづくりを軸とした中心市街地(まちなか)再構築プロジェクト」です。
(多世代・多文化交流の促進・新たな人の流れ)
令和7年度も「地域再生推進法人」である青年海外協力協会(JOCA)をはじめ、各種団体が参画する「生涯活躍のまち推進協議会」と連携し、「人生100年型 多世代交流コミュニティの実現」をコンセプトとする「駒ヶ根市版生涯活躍のまち構想」の実現に引き続き取り組んでまいります。
JOCAの運営する施設としては、昨年4月、小規模保育所「J‘s保育園駒ヶ根」が銀座通りに開園し、まちなかに子どもたちなど、新しい人の流れが生まれました。
こうした動きとともに、地域資源を活かした「駒ヶ根版ワーケーション」や「教育旅行」など、「学びと交流のプログラム」を進め、市内外の多様な人々が関わり合う場を創出していきます。
また、JICA協力隊OB・OGに再び駒ヶ根市を訪れていただき、市民活動などへの参加を促進し、関係人口の増加につなげる取り組みを新たに実施します。
(活躍の場づくり)
さらに、市民団体の活動拠点である「市民活動支援センターぱとな」の活用を通じて、多様な人々の「活躍の場」を創出してまいります。
(健康増進)
「ゴッチャウェルネス駒ヶ根」では、活動量計を使った健康づくり事業や、健康、介護予防に関する相談にあたっています。
また、健診を受けやすい環境づくりとして、各種健診や大腸がん検診の検体受付を、引き続き、土日・夜間を含めて行ってまいります。
(まちなかの魅力を高める)
こうした取り組みとあわせて、「こまがねテラス」や、「エリアプラットフォーム」とも連携し、中心市街地に魅力と賑わいを、さらに創出してまいります。
(優良建築物等の整備)
市街地のにぎわいや定住人口の増加など、まちづくりに必要と認める、民間の建築物の整備について、優良建築物等整備事業による助成を行います。
令和6年度では、空き店舗となっていた老朽建物の除却が終了し、7年度は、共同住宅、店舗等の建築の完成を目指します。職住一体による、まちなか居住の促進、商店街との連続性による通りの賑わいなど、中心市街地の再生を引き続き進めます。
(4)【竜東振興プロジェクト】
次に、4つ目の重点プロジェクト、竜東振興プロジェクトであります。竜東の玄関口となる、新宮川岸地区でリニア発生土を活用した圃場整備事業の推進と、この事業で創出される非農用地に農業振興を図る拠点施設の設置事業を引き続き進めてまいります。
圃場整備事業では、土地造成工事を進めつつ、圃場整備工事にも着手していきます。
また、拠点施設については、市民の皆さんの意見を反映した、基本設計の策定に取り組むとともに、施設完成後の管理、運営及び農産物の供給体制等の確保に向けた地元との調整を引き続き進めてまいります。
(竜東地域における農業振興と地域の賑わい・活性化の推進)
新たに整備を進めている拠点施設は、シルクミュージアムやふるさとの家などの既存施設と連携し、一体的に利活用することで、より多くの市民の皆さんの利便性向上と、観光客の皆さんへの魅力発信の強化との相乗効果を図ってまいります。特にシルクミュージアムでは、令和5年度に方向付けされた、カイコプロジェクトの計画スケジュールに沿って、6年度からスタートした、バイオ薬品の開発に向けた養蚕の担い手拡大や、返却される繭の利活用を推進するための仕組みづくりに向けた取り組みを進めます。あわせて、館内での動態展示のための準備を進めてまいります。
これらの取り組みを通じて、竜東地域の更なる農業振興や賑わいづくりにつなげていきます。さらに、駒ヶ根高原や中心市街地など、市域全体との連動を目指した取り組みも進めてまいります。
(5)【地域資源を活かした観光地域づくりプロジェクト】
次に、5つ目の重点プロジェクト、地域資源を活かした観光地域づくりプロジェクトであります。地域資源のブラッシュアップや情報通信技術の活用などにより、魅力的な地域を目指してまいります。
(駒ヶ根高原グランドデザインを基軸とした観光施策の展開)
駒ヶ根高原グランドデザインを基軸とした観光施策では、令和7年度の主な事業として、レンタサイクル事業や、Wi-Fiを利用したアンケートなどに取り組みます。
駒ヶ根観光協会と連携した、観光地周遊への仕組みづくりや地域資源を活用した新たな観光コンテンツの開発も進めてまいります。
また、早太郎温泉事業協同組合が行う早太郎温泉30周年事業への支援を行い、駒ヶ根高原の知名度向上に努め、新たな観光客獲得に向け、取り組みます。これらの事業を通じて、滞在型観光の充実や、さらなる地域資源の活用に取り組んでまいります。
(中央アルプス国定公園の魅力を活かした活用と適正な保全)
山岳観光では、本年度、指定から5周年を迎える中央アルプス国定公園の魅力を活かした利用と、適正な保全に努めてまいります。
登山者・観光客・住民の皆さんに「また来たい」と思っていただける、山岳観光都市を目指してまいります。
主な事業としては、空木岳登山道の改修や縦走路及び登山道の維持管理、檜尾小屋及びテント場の適正管理、中央アルプス国定公園の情報発信などを行い、魅力を活かした誘客を進めてまいります。
また、中央アルプスの魅力を広く発信するため、令和6年度に初めて実施した「信州山の日」タイアップイベントを引き続き開催し、山岳観光の魅力を多くの皆さんに伝えてまいります。
(6)【カーボンニュートラル推進プロジェクト】
次に、6つ目の重点プロジェクト、カーボンニュートラル推進プロジェクトであります。
(家庭への再生可能エネルギー施設促進・公共施設への再生可能エネルギー施設導入)
脱炭素社会実現に向けて、国が示す「脱炭素ロードマップ」の目標に基づき、公共施設への太陽光発電設備設置をはじめ、照明器具のLED化の促進、公用車への電気自動車導入に取り組みます。あわせて、省エネ家電の買い替えやグリーンカーテンの設置など、市民の皆さんの身近な取り組みに対する、えがおポイント交付などを通じ、カーボンニュートラルを推進してまいります。
また、県が実施する水力発電事業へ協力するとともに、要綱に基づいた適正な太陽光発電設備の設置を誘導してまいります。
2【共通基盤】
以上重点プロジェクトについて説明しました。
次に、それぞれの施策や事業を推進していくうえでの、共通基盤について説明します。
(1)【こまがねDX戦略の推進】
まず、あらゆる施策の共通基盤となる、DXの推進を、「こまがねDX戦略」に基づき推進してまいります。
令和6年度に検討に着手した「窓口改革プロジェクト」につきましては、7年度に具体的な検討を進め、新たに「窓口DX」のデジタルシステム実装により、職員の業務プロセス改革と、市民の皆さんにやさしい窓口の実現を目指してまいります。
そのほか、公共施設スマートロックの拡充や、市民の皆さんへの各種郵送通知に「デジタル通知」を導入するなど、引き続き、業務効率化と利便性向上に取り組みます。
また、中小企業のDX推進に向けた支援に取り組んでまいります。
3【基本目標】
次に、将来像を実現するための5つの基本目標に沿って説明します。
(1)【ひとづくり】
始めに、1つ目の基本目標の「ひとづくり」であります。
(妊娠期から子育て期の切れ目ない支援)
出産し退院した、母子に対し、心身のケアや育児のサポート等を行い、安心して子育てができるように、産後ケア事業に積極的に取り組んでまいります。
子どもたちの健やかな成長を支援するために、各種予防接種を実施し、疫病の発症やまん延を防ぐ取り組みを実施します。
乳幼児健診や相談を実施して、子どもたちの成長や発達を保護者と一緒に確認し、次の成長までの見通しを持った育児ができるよう取り組んでまいります。
(家庭・地域の子育て力の向上)
全てのお子さんや・若者の皆さんが、身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して取り組みます。
また、こども家庭センターを中心に、妊産婦や乳幼児の健康維持・増進や、子どもや子育て家庭に関する包括的な支援を実施します。
若者相談室では、義務教育後の年代の子どもたちや保護者も含め、誰でもどんなことでも相談できるよう取り組んでまいります。
利用者が増加しているファミリーサポートセンター事業については、サポーターの待遇改善を行い、より利用しやすい体制を整えます。
(幼児期の健全育成を推進)
駒ヶ根市の保育・幼児教育の指針である「保育・幼児教育ビジョン」に基づいた施設整備計画を進めるため、令和7年度より、美須津保育園と赤穂南幼稚園の統合に着手します。
また、ビジョンに基づき、保育・幼児教育の適正配置や適正規模、ニーズに合った保育士の配置、施設整備に取り組んでまいります。
より良い保育環境の確保や、保育士の負担軽減を図るため、保育士配置基準の改善や保育士の人材派遣制度の活用、保育補助員の配置を実施します。
(子どもの食育を推進)
「お弁当の日」を設定し、子どもたちに健全な食生活の意識付けをするとともに、家庭での食に対する意識高揚や、食育を推進してまいります。
また、増えています、食物アレルギーがある児童・生徒に対して、安全・安心な給食を提供できるよう、栄養士を配置し、対応してまいります。
老朽化が進んでいる竜東学校給食センターの在り方については、学校給食センター運営委員会へ諮問し、方向性を検討してまいります。
(学校教育の充実)
「内から育つひたむきな子」の育成にも、全力を尽くしてまいります。
ICT教育の充実を図るため、インターネット環境の整備や、機器の更新を行ってまいります。
増加している、不登校児童・生徒への支援として、不登校対策指導主事を教育委員会に配置するとともに、小学校には子どもと親の相談員、中学校には生徒相談員をそれぞれ配置します。あわせて、中間教室の見直しを行って、より利用しやすい体制や環境を整備してまいります。
また、子どもたちが安心・安全に学べる環境を整えるため、特別支援教育支援員や看護師、外国籍児童生徒支援員などを状況に合わせて配置し、特別支援教育支援員の質の向上も目指して取り組んでまいります。
学校施設の老朽化については、優先順位付けをして対応してまいります。また、小中学校のトイレの洋式化も、計画的に進めてまいります。
(学校・家庭・地域社会との連携強化による教育力向上)
学校支援ボランティアを募集し、学校が抱えるさまざまな課題について、地域の皆さんのお力もあわせ、解決に向けて取り組んでまいります。
また、保護者や地域の皆さんのご意向を反映し、開かれた特色ある学校づくりを、学校・家庭・地域が一体となって進めるため、コミュニティースクールを全小中学校で実施します。
子どもたちが自分自身の将来について、主体的に考え、行動できるよう、産学官等が連携して効果的なキャリア教育を実施してまいります。
(生涯学習の推進)
市内各地域の風土に根ざした自然、文化、歴史、伝統を学ぶ機会とともに、多様なライフスタイルに合った学習機会を提供してまいります。公民館の活動や住民の身近な学びの場である分館活動の推進を図り、地域の皆さんと一緒に、青少年の育成や十二天の森の整備・活用など、学びを通じた人づくりが地域づくりにつながる生涯学習事業を推進してまいります。
(文化財の保存と活用)
文化財につきましては、博物館と付属施設である郷土館、民俗資料館及び、館内の登戸研究所平和資料館の展示充実と活用を促進し、指定文化財の計画的な修理・保存を行い、市民に文化財の周知と学習機会の提供により活性化を図ってまいります。また、古文書等保存資料のデジタル化を進め、引き続き、埋蔵文化財の保存管理に努めてまいります。
(文化芸術活動の推進)
文化センターについては、建築後38年が経過し老朽化が進んでいることから、長寿命化を図るため改修基本計画に基づき、改修工事に着手しました。令和7年度は、継続して屋根及び外壁、空調設備の改修工事を実施します。
また、DX化を進め、オンラインでの予約状況の確認や、一部施設のオンライン予約を開始し利便性向上を図ってまいります。
図書館事業では、第4次駒ヶ根市子ども読書活動推進計画に沿って、小学1年生を対象にしたサードブック事業による本の配布など、若い世代の読書活動を推進してまいります。
さらに、児童・生徒の文化芸術や音楽を通じて生きる力を育むための事業として、ジュニア駒展、ジュニア和楽器隊や弦楽器教室、学校授業へのプロの講師派遣などに引き続き取り組んでまいります。
(市民スポーツの推進)
「信州駒ヶ根ハーフマラソン」は、選手・大会ボランティア・沿道の応援など・大会に関わる全ての皆さんが充実感を味わえる大会運営に努め、地域の活性化や駒ヶ根ファンを増やす機会としてきました。令和7年度をもって一時休止としますが、再開に向けて、さらなる魅力向上や運営体制を充実するため、具体的な検討を進めます。
令和10年(2028年)に長野県で開催される、第82回国民スポーツ大会に向けて、本格的に取り組みます。ホッケー競技会場の整備として、馬住ケ原運動場の夜間照明設備のLED化工事に着手します。
また、市民の皆さんのホッケーへの関心を高めるため、競技団体とともに普及・振興活動に努め、大会開催に向けた実行委員会の設置等、県をはじめ、中央競技団体、地元関係者や関係団体等と協議し、準備を進めてまいります。
(市民参画の促進と市民活動の推進)
市民参画の促進と市民活動の推進では、引き続き、市民活動支援センターぱとなを拠点として主体的な市民活動への支援に取り組んでまいります。
(地域コミュニティの活性化)
地域コミュニティの活性化では、令和5年12月に設けました「自治組織の在り方検討会」で講演会や研修を含む会議をこれまで8回行っています。人と人とのつながりや対話の重要性、支え合いや交流の場としての組織の役割などが指摘されており、令和7年度中を目途に提言を取りまとめていただく計画であります。これまでの議論を市民の皆さんにご理解いただき、広くご意見をお聞きする機会として、フォーラムディスカッションを開催してまいります。
(人権が尊重される社会の実現)
多様性を認め合い、差別や偏見がなく、一人ひとりの人権が真に尊重される社会を実現するため、人権尊重に関する啓発活動や人権教育に取り組むとともに、駒ヶ根市パートナーシップ宣誓制度による、性的マイノリティーや事実婚カップルなどの皆さんへの支援を引き続き行ってまいります。
また、犯罪被害者等支援条例を施行し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減や生活再建の支援について制度化するなど、誰もが安心して暮らしやすいまちづくりを推進してまいります。
(男女共同参画社会づくりの推進)
駒ヶ根市男女共同参画計画に基づき、互いに人権を尊重し、誰もが個性と能力を発揮できる、多様性に富んだ活力ある社会に向け、女性参画の促進、ワークライフバランスの実現、魅力ある地域の創出などに関するさまざまな施策を推進してまいります。
引き続き令和7年度も「あなたと私のいきいき講座」を開催し、幅広い観点からの啓発活動に取り組んでまいります。
(国際交流と多文化共生の推進)
国籍を超えた市民が相互に認め合い、多様性を尊重し、誰もが地域社会の一員として活躍できる社会づくりに向け、引き続き国際交流と多文化共生の取り組みを推進します。
駒ヶ根市には、全国に2カ所しかない、JICA青年海外協力隊訓練所や、協力隊OB・OGを中心に組織された青年海外協力協会(JOCA)の本部があります。市民の皆さんによる「みなこいワールドフェスタ」や、外務省との共催で本年度4回目を実施した「駒ヶ根フォーラム」などに引き続き取り組んでまいります。
ネパール・ポカラ市との友好都市交流事業では、昨年、ポカラ市の代表団の皆さんが駒ヶ根市を訪れ、関係者との懇談や市民の皆さんと交流しました。令和7年度は、駒ヶ根市がポカラ市を訪問し交流を深める予定です。
また、若い世代の国際感覚の醸成に向け、コロナ禍で休止していた中学生海外派遣国際交流事業を再開します。
本年4月13日から10月13日までの184日間、大阪・関西万博が開催されます。この万博開催を契機としたネパール文化交流事業を実施し、国際協力・国際理解のまちづくりをより一層推進してまいります。
(2)【健康づくり・支え合いの地域づくり】
次に、2つ目の基本目標の「健康づくり・支え合いの地域づくり」についてです。
(健康づくり習慣の普及)
少子高齢化の進展や、価値観・ライフスタイルの多様化などにより、疾病予防がますます重要となっています。駒ヶ根市の優先的な健康課題として、健康寿命の延伸には循環器病対策が挙げられます。専門職による啓発活動の強化や地域の多様な主体と連携・協働する取り組みにより、地域全体の健康意識を向上させるとともに、各種健(検)診の受診を促進します。
また、歯科健診事業では、新たに20歳と30歳を健診の対象に拡充することで、生涯を通じた歯・口腔の健康の保持・増進を図ってまいります。
(高齢者の保健・福祉・介護の体制整備)
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境を整備するため、医療・介護連携の強化を図るとともに、介護人材の確保を推進してまいります。
また、住民主体の支え合いの地域づくり事業、・認知症関連事業を一体的に社会福祉協議会に委託し、連携して多層的な生活支援体制を整えてまいります。
(健康保険、福祉医療制度の運営)
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の公平公正な確保に努め、収納率向上により制度の安定的な事業運営を目指してまいります。
また、特定健診の受診率向上に向け、保健事業による健康増進、予防活動に取り組み、健全な国保財政の運営に努めてまいります。
全ての方に切れ目のない保険診療を確実に提供できるよう、健康保険証廃止後の適正な運用に努めるとともに、「マイナ保険証」への切り替えによるメリットについて、積極的に啓発してまいります。
国民健康保険は、国民健康保険税の県内市町村の平準化に向けた県のプランに沿って、令和9年度までに、二次医療圏の医療費指数を段階的に統一するよう準備を進めてまいります。
福祉医療費は、18 歳までの子どもの無料化のほか、障がい者や母子・父子など、医療費の経済的な負担軽減を引き続き実施してまいります。
(障がい者の生活支援と社会参加の推進)
障がい者の皆さんが、安心していきいきと暮らし、自立に向けた生活を送ることができるよう、障がい等に関する理解の促進や重度の障害がある方の地域生活の支援、サービスの拡充、就労環境の充実を図ってまいります。
(生活困窮者への支援)
生活困窮者等への支援としては、自立相談や家計改善支援などの包括的な支援の充実を図るとともに、地域生活課題を抱えながらも、自ら支援を求めることが難しい人に必要な支援を届けるアウトリーチ事業を継続し、生活困窮者等に寄り添いながら、自立に向けた支援に取り組んでまいります。
(3)【ひとの流れづくり】
次に、3つ目の基本目標の「ひとの流れづくり」についてです。
(地域資源を活かした魅力ある観光地域づくり)
駒ヶ根市への観光客は、コロナ禍前の水準に迫る回復をしており、外国人客も増加しています。魅力ある観光地として駒ヶ根市を選んでいただけるよう、地域の価値を高める観光地域づくりを推進し、誘客効果を高める事業を進めてまいります。
令和7年度は、コロナ禍で途絶えていた台湾・台中市との交流を復活し、インバウンドの促進も見据えた関係性構築に努めます。
観光事業者の付加価値向上のための支援も継続し、施設整備や商品企画などを行うことで、高付加価値サービスが提供できるための支援を行ってまいります。
また、早太郎温泉の湯量確保のため、第5号井戸の掘削に取り組み、早太郎温泉の事業継続、魅力向上に努めます。
駒ヶ根観光協会と連携し、銀座NAGANOを利用したPRイベントを実施し、駒ヶ根の魅力発信を都市圏に向けて行い、新たな客層の取り込みに努めてまいります。
(移住・定住の推進)
「信州駒ヶ根暮らし推進協議会」と連携して、都市圏でのセミナーや相談会、市内での体感会を通じて、駒ヶ根市の魅力を伝え、移住・定住に繋げてまいります。 令和7年度は、国が積極的に取り組むとしている、二地域居住の推進に努めます。
また、引き続きマイホームの取得促進の補助を行い、子育て世代の定住を図るとともに、空き家の掘り起こしを進め、定住希望者に提供できる物件確保や補助制度を継続してまいります。
(関係人口の創出・拡大)
さまざまなかたちで駒ヶ根市に思いを寄せる人々が、多様な形で、市民の皆さんとともにまちづくりや地域づくりに関わるような社会を目指し、関係人口の創出や拡大に取り組んでまいります。
生涯活躍のまちづくりで取り組んでいる「ワーケーション」や「教育旅行」の誘致拡大、「それ、駒ヶ根でできます」をキャッチフレーズとしたプロモーションなどに官民連携して取り組みます。
(4)【しごと・ものづくり】
次に、4つ目の基本目標の「しごと・ものづくり」についてです。
(優良農地の確保と有効活用・農村環境の保全)
10年後の地域の農用地利用の姿を明確にするため令和6年度末に策定する「地域計画」に沿って、農用地の適切な利用増進や耕作放棄地の拡大を防ぐための取り組みを進めてまいります。
また、中山間地域等直接支払い制度や多面的機能支払交付金事業を活用して、農地や農業施設の保全への取り組みを続けることで、農村地域が持つ機能の維持と発揮を図りつつ、持続可能な農業の実現を目指して取り組んでまいります。
農作物被害を防止するための有害鳥獣駆除対策事業にも引き続き取り組みます。ニホンザルの出現回数が増えると、市民生活や観光等に影響が大きいため、引き続き、庁内各部署や地域と連携した取り組みを図ってまいります。
(暮らしを豊かにする魅力ある地域農業の創出)
農業を取り巻く環境は、従事者の高齢化、担い手や後継者不足、燃油や生産資材の高騰、国内外の産地間競争の激化など、益々厳しさを増しています。かつてないスピードで変化する社会構造と、そこから生まれる新たなニーズに即応できる地域農業の体制確保を目指し、「駒ヶ根市地域農業ビジョン」の見直しも含め、駒ヶ根市営農センターを中心に、持続可能な地域農業の実現に向けた取り組みを進めてまいります。
さらに、令和6年度に発生した、いわゆる「コメ不足」による米の需要増加と価格の高騰や、制度改正に伴う「転作農地の5年水張りルール」への対応の影響等により、生産状況の変化が懸念されることから、引き続き、生産者の安定的な収入確保に向けたさまざまな調整を図ってまいります。
(新しい技術を活かしたスマート農業の推進)
農業を取り巻くさまざまな課題解決の手段として、スマート農業機械の導入補助事業を引き続き実施するとともに、研修機会の提供を行うなどの支援を行います。
(多面的機能を発揮して暮らしを守る森林づくり)
森林は、木材生産のみならず、多面的機能を有しており、特にカーボンニュートラルの視点から重要な資源です。市域の75%を占める森林が、こうした機能を十分に発揮し、豊かな市民生活につなげるために、駒ヶ根市森林整備計画を基に整備を推進してまいります。
森林環境譲与税等を活用した林業振興事業や林道開設・改良事業、松くい虫防除対策事業にも継続して取り組みます。令和7年度は、上伊那植樹祭の会場となる「古城公園」整備の取り組みを通じ、より多くの市民の皆さんに、森林への関心を高めることを目指してまいります。
(活力ある商業・サービス業の振興)
商業・サービス業の振興では、それぞれの店が消費者ニーズに応じた商品やサービスを提供し、魅力的で個性的な力をつける必要があります。
そのために、商工会議所と連携して商業環境の整備や経営力強化を支援してまいります。
また、駅前立体駐車場の改修工事を行い、安全性確保に努めます。
(人が集まる「まちなか」の魅力づくり)
「まちなか」の魅力づくりのため、中心市街地の賑わいづくりや、楽しみの創出が必要です。
KOMA夏や、昨年復活したこまちバルなど、中心市街地で行うイベントへの支援を行います。
また、こまがねテラスプロジェクトや駒ヶ根まちなかエリアプラットフォームの活動を官民連携で推進してまいります。
(新たな高付加価値産業の振興と企業誘致の推進・地域を支える中小企業の経営基盤強化と人材の創出)
ものづくり産業は、駒ヶ根市の産業の大黒柱であります。
物価高騰や円安などにより企業収益が悪化しており、テクノネット駒ヶ根による人材育成を進め、企業体質強化に努めます。
深刻化している人材不足への支援策では、求人活動や広告、遠距離通勤の費用の補助などを継続してまいります。
また、企業誘致では、令和6年度に行った企業立地ニーズ調査を基に、駒ヶ根市へ投資を検討している企業にアプローチを行い、誘致を進めるとともに、必要となる産業用地開発を検討してまいります。
さらに、稼ぐ力の創出を目指して行った、BEAMSとの連携事業を継続し、企業の新たな付加価値向上、マーケティング力向上に努めてまいります。
(5)【安心・快適なまちづくり】
次に、5つ目の基本目標の「安心・快適なまちづくり」についてです。
(資源循環型社会の形成)
環境衛生対策では、令和7年度からスタートします「駒ヶ根市一般廃棄物処理基本計画」に基づき、リデュース、リユース、リサイクル、リプレイスの4Rの取り組みを図り、4月からの製品プラスチックの一括収集、再商品化、また使用済小型家電製品の回収などの取り組みにより、更なるごみの削減、資源化を推進してまいります。
(環境保全の推進)
資源物回収、不法投棄パトロール、河川や地下水の検査、騒音測定といった地道な取り組みを通じ、第3次環境基本計画で将来像に描く「自然資源を育み、活用し、豊かなくらしを未来につなぐまち」の実現に向けて、市民や事業者の皆さんとともに進めてまいります。取り組みや成果は、環境白書として作成し、公表します。
(安心して暮らせる住環境の整備)
都市公園が安全・安心な憩いの場として市民の皆さんにご利用いただけるよう、「公園施設長寿命化計画(第2期)」に基づき、計画的な修繕や更新を実施します。令和7年度は、国の6年度補正予算と併せ、南割公園、飯坂公園、飯坂東公園の遊具等の更新を行います。
また、適切な管理が行われていない空き家が増加し、防災、衛生、景観など地域住民の生活環境に影響を及ぼしています。一方で、地方移住への関心の高まりから空き家の活用は重要となっています。「第2期駒ヶ根市空家等対策計画」の計画期間満了を迎え、引き続き、空き家等対策を総合的、計画的に実施するため、令和7年度は「第3期駒ヶ根市空家等対策計画」を策定し、空き家の発生の抑制や利活用など、地域や関係機関等と連携して、空家等対策を一層推進します。
市営住宅は、困窮する世帯に対する住宅セーフティネットとして、適正なストックの更新・維持管理を行います。あわせて、効率的・効果的なマネジメントと、市営住宅のライフサイクルコストの縮減を図り、安心・安全な住環境の整備に努めてまいります。令和7年度は、「駒ヶ根市公営住宅等長寿命化計画(第3期)」に基づき、ユニットバスの設置やサッシの断熱、トータルリフォームの実施設計など、住環境の整備を計画的に行ってまいります。
(生活に密着した道路整備の推進)
生活道路は、重要なライフラインであります。
危険箇所や老朽箇所の修繕につきましては、各区の要望等に基づき、緊急度などの優先順位を踏まえて取り組みます。橋梁や舗装は、長寿命化修繕計画に基づき改修等を進めてまいります、特に橋梁は、中央自動車道に架かる、大徳原橋の撤去を行います。
また、近年、身近な道路での事故が多くなっていることから、通学路の安全対策として歩道整備、グリーンベルトの設置とゾーン30プラスの取り組みを進めてまいります。
(幹線道路網の整備)
市道の幹線道路は「道路整備プログラム」に基づき、南北軸である伊南バイパスと新春日街道線(広域農道)を結ぶ東西軸としての光前寺南線、通学路安全対策として新春日街道線・赤須町線の歩道整備、竜東地区の幹線道路である本曽倉線の整備を、それぞれ引き続き進めてまいります。
また、都市計画道路中割経塚線の伊南バイパス東側の未整備区間について、事業区域内の物件調査と用地補償の一部に着手します。
都市計画道路中割経塚線の整備を進め、東西間交通の円滑化、安全・安心の歩行空間の形成等、市の交通課題の解決に向けて取り組んでまいります。
(地域公共交通の確保)
超高齢社会、人口減少社会における市民の移動手段の確保という大きな課題に対し、本年度実施した市民アンケートの結果も踏まえ、新たな「地域公共交通計画」を策定し、課題解決を図ってまいります。
ドライバー不足が大変厳しい状況にあります、交通事業者に対しましては、新たに人材確保に向けた補助制度を開始します。
「こまタク」については、AI予約配車システムの改善などにより、さらなる利便性の向上を図ってまいります。
現在実証実験を行っています「公共ライドシェア meemo(ミーモ)駒ヶ根」は、本年度の実証結果を踏まえ、令和7年度も引き続き、実証実験に取り組み、効果の検証を行います。
3年目となる山麓周遊バス実証実験「さんさんバス」につきましては、2年間の実施結果を検証・反映し、実装に向けた課題解決を図ってまいります。
JR飯田線の活性化のため、引き続き沿線自治体等と連携してイベント列車の実施などに取り組みます。
「リニア中央新幹線」は開業時期が延期となりましたが、その効果を地域活性化に最大限活かすため、長野県駅から駒ヶ根市までの2次交通、さらに駒ヶ根市内の3次交通の構築に向けて、引き続き県や周辺市町村、関係団体等と連携して検討を進めてまいります。
(上下水道事業の持続と安全・安心)
水道事業では、基幹管路の耐震化、老朽化した水道管の更新及び原配水池の機械設備等の更新を行うとともに、小規模の配水池の改良及び更新を計画的に進め、安全で安心な水道水の安定供給に努めてまいります。
下水道事業では、さらなる接続促進に取り組み、水洗化率の向上を目指すとともに、駒ヶ根浄化センターの設備等の改築及び耐震補強を計画的に進めます。
維持管理が重要となっており、上下水道事業の持続可能な事業運営のために、計画的な更新等と適正な維持管理に積極的に取り組み、併せて広域化等の検討を進めてまいります。
(景観に配慮したまちなみの創造)
また、駒ヶ根市の大切な財産である美しい景観を後世に伝えていくため、景観条例、景観計画に基づく規制や誘導に取り組んでまいります。
(激甚化する災害への対策強化)
近年、集中豪雨などにより全国各地で大規模な災害が発生しています。幸い駒ヶ根市においては大規模災害の発生はありませんが、地形が急峻で地質が脆弱なため、土砂災害等が起こる危険性は高いと言えます。
土砂災害を防ぎ、住民の皆さんの生命・財産を守るため、流域の関係者が協同して減災・防災に取り組む流域治水の推進を図るとともに、土砂災害危険区域を中心に国・県とともに砂防事業、急傾斜対策事業等について、地域の皆さんと連携し事業促進を図ってまいります。
また、災害復旧作業を迅速に行えるよう、地籍調査事業を引き続き推進してまいります。
「駒ヶ根市耐震改修促進計画(第3期)」に基づき、所有者にとって「耐震診断」や「耐震改修」を行いやすい環境の整備、負担軽減のための支援を行います。令和7年度は、木造住宅の「耐震診断」及び「耐震改修」に対する補助をそれぞれ拡充し、耐震改修を一層促進します。
(地域防災力の強化)
近年、地球温暖化に伴う異常気象により、大規模な自然災害が各地で起きています。また、昨年「南海トラフ地震臨時情報」が発表されました。予想される大規模災害に備え、防災・減災対策の強化に引き続き取り組んでまいります。
令和7年度は、新防災行政無線システムの運用開始や、庁舎自家発電機の長時間稼働に向けた設備の充実を図ってまいります。
さらに、自主防災会における防災資機材・災害用備蓄資機材の更なる充実を支援してまいります。
また、消防団の機能や組織を維持するため、消防団コミュニティ施設や機関車両を更新するとともに、準中型自動車やバイクの免許取得補助制度を継続し、新規団員の確保につなげてまいります。
(防犯・交通安全・消費生活対策の推進)
安全・安心なまちづくりのため、警察や関係団体と協力し、防犯活動や交通安全推進活動にも力を入れます。
SNSを利用した投資やロマンス詐欺など、近年、特殊詐欺は多様化、被害額が高額化しています。また、犯罪の加害者になりかねない闇バイトは、SNSで「簡単、高収入」といった甘い言葉で若年者を誘っています。善良な消費者がこうしたトラブルに遭わないよう、身近で相談しやすい消費生活センターの運営につとめるとともに、警察署や長野県の消費生活センターなどの関係機関との連携強化、住民に向けた広報活動を通じ、消費生活対策を推進してまいります。
4.【むすびに】
初めに申し上げました通り、時代は大きな節目を迎えています。民主主義の危機だけでなく、経済面でも曲がり角に差し掛かっています。長く続いた、デフレは昨年来からの、さまざまな物価上昇に加えて、日銀の利上げによって様相を変え、むしろ、インフレの入り口に立っていると考えます。世界情勢をみても、米国のトランプ政権が関税引き上げなど、予測困難な政策を始めたことをきっかけとして、一層、不安定さを増しています。こうした情勢が、私たちの暮らしに、どう影響するのか。現時点で見通すことは困難な状況です。
駒ヶ根市としては、国内外の動きをしっかりと見据え、適切な対応をするべく、全力で取り組んでまいります。議員の皆さん、市民の皆さんの一層のご支援をお願いし、令和7年度の施政方針とします。
令和7年度市長施政方針 (PDFファイル: 392.3KB)
バックナンバー
令和6年度市長施政方針 (PDFファイル: 698.5KB)
令和5年度市長施政方針 (PDFファイル: 711.8KB)
令和4年度市長施政方針 (PDFファイル: 759.1KB)
令和3年度市長施政方針 (PDFファイル: 830.1KB)
令和2年度市長施政方針 (PDFファイル: 532.1KB)
平成31年度市長施政方針 (PDFファイル: 571.3KB)
平成30年度市長施政方針 (PDFファイル: 492.4KB)
平成29年度市長施政方針 (PDFファイル: 701.7KB)
平成28年度市長施政方針 (PDFファイル: 609.5KB)
平成27年度市長施政方針 (PDFファイル: 988.1KB)
平成26年度市長施政方針 (PDFファイル: 459.1KB)
平成25年度市長施政方針 (PDFファイル: 461.5KB)
平成24年度市長施政方針 (PDFファイル: 540.9KB)
平成23年度市長施政方針 (PDFファイル: 602.0KB)
平成22年度市長施政方針 (PDFファイル: 521.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
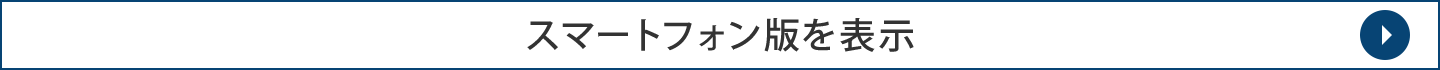








 総合トップ
総合トップ 組織から探す
組織から探す 相談窓口
相談窓口 お問い合わせ
お問い合わせ 行政サイト
行政サイト 移住定住サイト
移住定住サイト 子育てサイト
子育てサイト 観光協会
観光協会
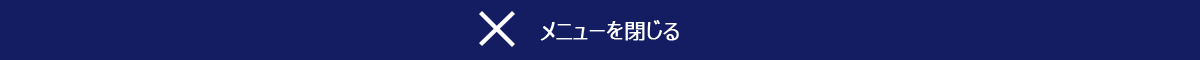

更新日:2025年02月27日