令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりました
民法改正により、令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
18歳になると変わること
成年になると、親の同意がなくても多くのことができるようになります。
例えば、携帯電話を購入する、クレジットカードを作る、ローンを組む、一人暮らしの部屋を借りるといったさまざまな契約ができます。一方、飲酒や喫煙、競馬・競輪などはこれまでと同様、20歳にならないとできません。
成年年齢引き下げにより懸念される消費者トラブル
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法の未成年者取消権を行使して取り消すことができます。これは未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
成年に達すると、自分の意志で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
社会経験に乏しく、未成年者取消権がなくなったばかりの成年を狙う悪質な業者もいたりと、消費者トラブルに巻き込まれやすい傾向があります。
若者に多いトラブル事例
サイドビジネス商法

SNS上の知り合いなどから「副業で簡単に稼げる」「儲かるためのノウハウが学べる」などと誘われます。お金がないと断っても、「初期投資分はすぐに元が取れる。今から消費者金融で借りればよい」などと強引に契約を高額な商材を購入させられたりします。
うまい話には裏がありますし、簡単に儲かる話なんてありません。怪しいとおもったら、きっぱりと断りましょう。
インターネット通販

インターネット通販での定期購入や、フリマアプリなどでのトラブルが多く寄せられています。
1回きりのつもりで初回お試し価格の商品を購入したところ、翌月同じ商品が届いて初めて定期購入だったと気づくケースが多いです。
インターネット通販は、クーリング・オフ制度の対象外です。返品・交換については販売事業者ごとに定めている規約に従うことになります。事前によく確認し、よく理解してから注文しましょう。
また、フリマアプリで画像とは違うものが届いたり、返品しようとしても対応してもらえなかったりといったトラブルもあります。
アプリの運営会社はあくまでも仲介だけで、トラブルの解決については、原則当事者同士が行います。
成年に達して一人で契約する際に注意すること

契約には責任も生じます。本当に必要な契約かどうか、よく検討しましょう。契約にはさまざまなルールがあり、そうした知識がないまま安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
契約に関する知識を学び、ルールを知ったうえで、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。
おかしいなと思ったらすぐに相談を
いったん成立した契約は、原則取り消すことができません。
しかし、事業者による不当な勧誘により契約させられてしまったり、クーリング・オフが行使できる取引だった場合など、契約を取り消すことができる場合があります。権利を行使できる期間が決まっているので、おかしいと思ったらすぐに駒ヶ根市消費生活センター、または、消費者ホットライン(局番なし188)へご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
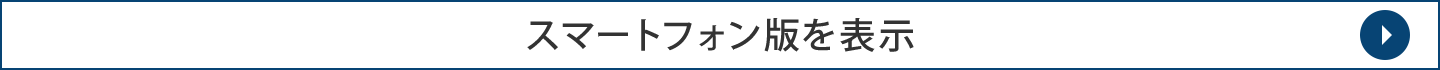








 総合トップ
総合トップ 組織から探す
組織から探す 相談窓口
相談窓口 お問い合わせ
お問い合わせ 行政サイト
行政サイト 移住定住サイト
移住定住サイト 子育てサイト
子育てサイト 観光協会
観光協会
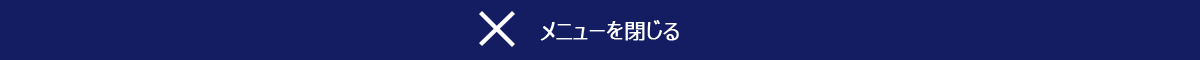

更新日:2022年04月01日