市長が市政を解説
市長が市政を解説は、市報こまがねに毎月掲載しています。
市の窓口をリニューアル(令和8年2月号)
財政再建は着実に進展(令和8年1月号)

将来負担比率の推移
暮らしの安定には家計をしっかり管理しなくてはと考えると思います。市も同様です。素晴らしい計画を作っても実行できる基盤が安定していなければ始まりません。市長就任以来、財政再建を重要課題と定め、取り組んできました。
自治体の財政状況を示す指標に「将来負担比率」があります。ざっくり申し上げると、収入・貯金の総額に対する借金の比率です。家計に例えると、給料や貯金に対する住宅や車のローン残高の比率に当たります。350%(3.5倍)を超えると、総務省から早急な改善を求められます。
市は平成29~30年度に約200%近くに達していました。全国市町村で最悪に近い水準で、関東財務局からも赤信号と指摘されていました。しかし、昨年11月の市報で報告しました通り、令和6年度は53.9%まで低下しました。
ふるさと寄付が最高額を更新し続けるなど収入が増え、一般会計の基金残高が令和6年度は2年度から倍増の51億8千万円となったことなどが主な要因です。借金返済も進んでいます。ようやく出口が見え、昭和伊南総合病院の移転・新築など重要事業の準備が整いつつあります。今後も着実に再建へ取り組みます。
第6次総合計画の策定へ(令和7年12月号)

駒ヶ根のまちなみ
「それ駒」グッズを充実(令和7年11月号)

市のキャッチフレーズ「それ、駒ヶ根でできます」をアピールしようと、ロゴを作成しPRを進めています。バッジのほか、ポロシャツも作成しました。私も、さまざまな機会に着ていますが、好評だと自負しています。
これは、市の戦略を探る「シン“KOMAGANE”プロジェクト」の1つで、相模女子大の皆さんからいただいた政策提言から生まれました。さまざまな分野や素材を一つの看板のもとに結集し発信することで、効率的で強力に届けようとの狙いです。ロゴのデザイン制作は、市内の女性デザイナーにお願いしました。
今夏からは、新宿―駒ヶ根間の高速バスにラッピング広告を掲載しました。1日1往復ですので機会は限られますが、中央自動車道やバスタ新宿などでぜひ探してみてください。 ロゴを使ったグッズはさらに充実します。秋から長袖ポロシャツに加え、ウインドブレーカーも登場。バッグやクリアファイルなどもそろえていく計画です。
また「できますメニュー」を集めてインターネットで発信する取り組みも進めます。観光や飲食など駒ヶ根ならではの楽しみを発信します。市を売り込む旗印として、さらに活用していきます。
公共交通の新計画策定(令和7年10月号)

公共ライドシェアユーザー体験の様子
令和3年度に策定した駒ヶ根市地域公共交通計画は本年度、最終年度を迎えます。市民の皆さんの「足」を支えるため、市として、さまざまな取り組みを重ねてきました。これまで5年間の成果と反省を踏まえ新たな計画を策定し、来年度から、さらに進めていきます。
現在の計画は交通事業者や自治会などの利用者、学識経験者のほか、県や国土交通省の担当者が参加した協議会と、交通事業に詳しいNPO法人も加わり策定しました。安心して生活できることや、効率的・持続可能など6つの方針の実現を目指し、事業を進めています。こまタクの利便性向上のため、AIを使った予約配車システムを導入。高原を中心に観光スポットをつなぐ山麓周遊バスや、タクシーを補うために公共ライドシェアの実証実験など新たな事業も行ってきました。
令和6年度には市民アンケートを実施。こまタクの認知度が半分程度であることや、4割の方が公共交通が不足していると考えていることなどが分かりました。こうした結果を踏まえ、新たな計画の重点事業を検討します。市議会や市民の皆さんのご意見・ご提案をいただく機会もつくっていきますので、ご協力をお願いします。
ビジョン実現へ 保育施設整備(令和7年9月号)

交流会の園児の様子
市は令和5年3月、子どもたちのための「保育・幼児教育ビジョン」を専門家や保護者の皆さんと作りました。時代の変化に対応し、より良い環境を整えることが狙いです。
このビジョンに沿って保育園・幼稚園の施設整備を進めています。あわせて想定を超えるスピードで進む少子化も踏まえなくてはなりません。そこで令和8年度に赤穂南幼稚園を閉園し美須津保育園と統合。赤穂南幼稚園を撤去し新たな保育園を建設、令和10年度の開園を目指します。2園を統合することで一定人数のお子さんが集まり、充実した保育・幼児教育を進めることができます。
また、新園は隣接する赤穂南小学校と連携し、豊かな学びと育ちにつながる交流を進めます。総定員100人で、3歳未満のお子さんも受け入れます。保育士の声も聞き施設の詳細を詰めていきます。
また、園児数減少の影響で下平幼稚園は本年度末で閉園します。園児の皆さんは近隣の飯坂保育園などへ通うことになり、既に交流を始めています。今後も工夫を重ね、ビジョンに沿った保育・幼児教育の実現に取り組んでいきます。
ホッケー、国スポへ準備加速(令和7年8月号)

ホッケー競技場完成予想図
令和10年度に長野県で開く国民スポーツ大会。駒ヶ根市は飯島町とともに、ホッケー競技の会場となります。競技場の工事や実行委員会の発足など、いよいよ本格的な準備が進んでいきます。
競技場は馬住ヶ原運動場を改装し設置します。本年度はLED照明を取り付け、来年度の完成を目指し工事が本格化しています。グラウンド全面をホッケーに合う砂入り人工芝に。一部には陸上競技用トラックを入れ、多目的利用にも対応します。約400人を収容する仮設スタンドも設け、トイレや倉庫なども改装・新設し、スムーズな大会運営を目指します。
実行委員会には行政や議会、スポーツや教育、宿泊や飲食など幅広い分野の関係者が参加予定です。県や飯島町などとも連携し、全国の選手をお迎えします。
本年、ホッケー協会から県内初の公式ホッケータウンに認定されました。国スポへ向け選手育成にも取り組みます。スティックを握り、汗を流す選手を見かけたら、ぜひ温かな応援を送ってください。
ふるさと寄附 過去最高を5年連続更新(令和7年7月号)

応援したい自治体を選んで納税する「ふるさと寄附」。市へ令和6年度に寄せられた総額は前年度から2倍近くの12億6,825万5,700円と、過去最高となりました。私が市長に就任する前の令和元年度の3億4,500万円と比べますと、3倍以上に伸びたことになります。寄附額による収入増は、市の課題である財政再建につながります。
増えた要因は返礼品の人気の高まりです。とりわけ、市内の企業が開発した櫛に注目が集まりました。独自技術で施したメッキにより静電気などを抑え、スムーズに髪をとかすことができます。芸能人や美容師のほか、贈答用としても評判となり、大ヒットとなりました。ウイスキーやビールなど酒類、マツタケなど農林産物も好調です。
こうした返礼品は市内の産品です。企業や生産者の皆さんが培ってきた技術やアイデアが高い評価を得たからこそ、ふるさと寄附につながっています。そのため市では、さまざまな産業の力を高めることが重要と考えます。昨年度から、セレクトショップを展開するBEAMSと市内企業が協力、新商品の開発事業をスタート。既にアウトドア用品などが生まれています。引き続き、力を合わせて取り組みを進めます。
中心市街地に防災広場(令和7年6月号)

完成した町部防災倉庫
DX化へ アナログ規制見直し(令和7年5月号)

職員を対象に実施した、アナログ規制見直しの勉強会
市は令和7年度、行政手続きの「アナログ規制」見直しに取り組みます。これまで通りに人による確認や書類提出などを必要としたままでは、インターネットなどを使ったデジタルによる手続きは進みません。こうしたアナログ規制を減らすことが、デジタル化の大前提となるためです。
見直し対象は、214の条例や166の規則、305の要綱などとなります。具体的には、対面による講習や紙の証明書の提出、役所への訪問を求める規制などが想定されます。このようなアナログ規制を8月までに洗い出し、秋から各課が見直し作業を始める予定です。
その際には、見直しや残さざるを得ないものなどに分類します。そのうえで、条例や規則等の改正を順次行っていきます。
市は、国のデジタル庁がアナログ規制見直しで個別型支援事業を行う、31自治体の一つに選ばれました。このため、同庁の地方アナログ規制推進班から技術支援を受け、進めることができます。
システムの導入だけでデジタル化は進みません。技術進歩にふさわしい、行政の仕組みに変えていくことが重要となります。市民サービス向上のため、地道な作業に取り組んでいきます。
市から1年生にエール(令和7年4月号)

小学1年生に贈呈するバックパック
桜が開く4月は新入学の季節です。市は今年も、希望される小学1年生に通学用バックパックと本をお贈りしました。「子育て全力応援」を宣言し、展開している施策の一つです。元気に背負って通う子どもたちの姿を見ることが楽しみです。
バックパックは、市と包括連携協定を結んでいる、大手アウトドア用品メーカー、株式会社モンベルの製品です。保護者らの経済負担の軽減にと、令和5年度入学の小学1年生から贈呈を始めました。革製ランドセルに比べ軽く、アルプスを描いた、市独自のデザインも施されています。今回はブラックが加わり、4色から好きな色が選べます。
また、読書に親しんでいただこうと、お子さんの発達段階に合わせて本の贈呈も行っています。6カ月と2歳3カ月に続いて、小学1年生が3回目となります。年齢にふさわしい内容の30冊の中から、お好きな1冊を選べます。
バックパックと本は、各小学校で行われた、1日入学・保護者説明会でお贈りしました。4月からの小学校生活を思いきり楽しまれることを祈っています。
新宮川岸地区が新展開へ(令和7年3月号)

工事中の新宮川岸交差点付近
- この記事に関するお問い合わせ先
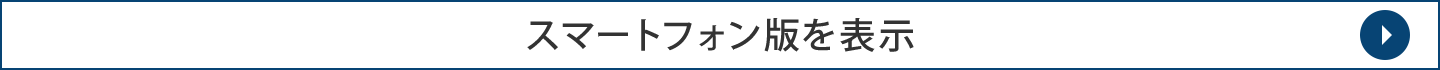








 総合トップ
総合トップ 組織から探す
組織から探す 相談窓口
相談窓口 お問い合わせ
お問い合わせ 行政サイト
行政サイト 移住定住サイト
移住定住サイト 子育てサイト
子育てサイト 観光協会
観光協会
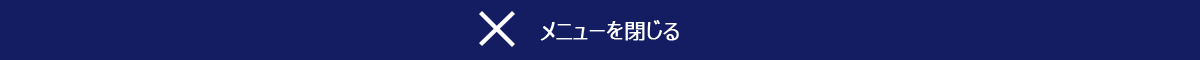

更新日:2026年01月28日