9月10日は下水道の日
下水道は普段は目に見えませんが、台所やお風呂場、トイレなどから出る生活排水や汚水、工場廃水を魚が住める水質まできれいにし、河川に戻す役割を担っています。
正しい使用にご協力を
下水道施設は、みんなの財産です。正しく使わなければ、不具合や故障などの原因になります。
下水道の維持管理にかかる経費は、皆さんからいただく下水道使用料でまかなっています。維持管理費を抑え、施設を長く使えるようにご協力をお願いします。
生活の中で使った水(下水)がきれいになるまで
駒ヶ根市公共下水道区域内で使われた水は「駒ヶ根浄化センター」という下水処理場で、さまざまな処理がされます。処理を終えて、きれいになった水は河川に放流され、私たちの生活に再利用されます。
私たちが日常生活で出した汚れた水(下水)は、どのようにしてきれいになるのか、一緒に見ていきましょう。

左から処理場に入ってくる水・微生物が浄化した水(下に溜まっているのが微生物)・微生物が分解した水の上澄みを消毒した水(放流水)

下水処理の流れ(公益社団法人 日本下水道協会HPから引用)
駒ヶ根浄化センター処理の流れ
1.沈砂池(ちんさち)

処理場に集められていた下水は、まず沈砂池という池でゆっくりと流されます。砂を沈め、大きなゴミは機械で取り除かれます。
2.沈砂池を通ったあと、下水を次の処理工程に送る管


直径60センチメートルの管で送ります
3.最初沈でん池

沈砂池から送られてきた下水は、この池で2〜3時間ほどかけてゆっくり流れます。流れる間に、沈でんしやすい細かいゴミなどは底に沈みます。
この沈んだゴミなど(生汚泥)は、汚泥処理施設へ送られます。
3.微生物が大活躍 エアレーションタンク(反応タンク)


ここで「最初沈でん池」から送られてきた下水が微生物のいる水槽に入れられます。微生物は窒素やリンの除去、汚れを分解します。
4つの水槽(そう)があり、空気を送り込む槽と送り込まない槽を組み合わせることで、汚水処理を行っています。
下水は、これらの槽で8〜9時間ほどかけてゆっくりと流れていきます。その間に、微生物が下水中に溶けている汚れを栄養として吸収し、水や炭酸ガスなどに分解して繁殖していきます。また、汚れを取り込んだ微生物は沈みやすいスポンジのような泥となり、沈でんしていきます。この工程により下水が浄化されていきます。
4.最終沈でん池


エアレーションタンクで沈でんしやすくなった微生物(活性汚泥)は、ここで4〜5時間ほどかけてゆっくりと流れていくうちに、池の底に沈んでいきます。上澄みのきれいな水だけを塩素混和池へ送ります。
沈殿した微生物を含んだ泥(活性汚泥)の一部は、種汚泥としてエアレーションタンクへ戻し、ふたたび利用します。残りの汚泥は汚泥処理施設へ送られ処理されます。
汚泥処理施設で水分を絞った汚泥は、主にセメント工場に運ばれます。その後、汚泥は高温で焼かれ、セメントの原料になります。
5.塩素混和池
最終沈でん池から送られてきた処理水は、この池で消毒され河川へ放流します。消毒には、次亜塩素酸ナトリウムを用います。処理水が塩素混和池へ流入する場所で塩素を入れ、およそ30分間接触させ、大腸菌を滅菌しています。
下水処理場で処理できないものは流さないで

「ちょっとくらいなら」という気持ちが、下水管のつまりやポンプの故障を引き起こし、周辺住宅などへ迷惑をかけることにつながる可能性があります。正しく使いましょう。
- この記事に関するお問い合わせ先
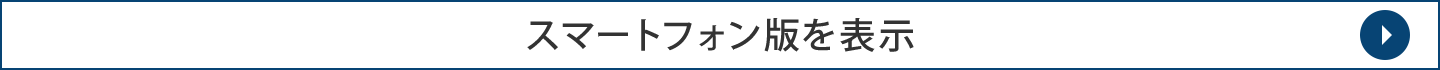








 総合トップ
総合トップ 組織から探す
組織から探す 相談窓口
相談窓口 お問い合わせ
お問い合わせ 行政サイト
行政サイト 移住定住サイト
移住定住サイト 子育てサイト
子育てサイト 観光協会
観光協会
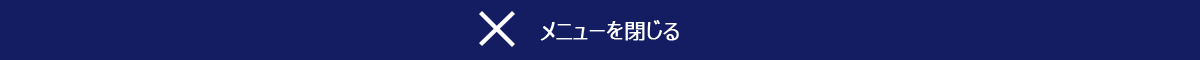

更新日:2025年08月13日