介護保険の運営と財源のしくみ
介護保険の運営
介護保険の運営は市町村が行うことになっていますので、皆さんがお住まいの駒ヶ根市が「保険者」となって運営します。
保険者(市)の役割
- 介護保険の財政運営
- 65歳以上の人の保険料賦課徴収
- 要介護認定
- 保険給付
- サービス提供機関の環境整備
財源のしくみ
介護保険会計の区分
介護保険の費用は、次の二つに分かれています。
- 保険給付費用 サービス利用にかかる8~9割相当分の保険給付費です。
- 事務的費用 第1号被保険者保険料の賦課徴収、介護認定など介護保険の運営に必要な1.以外の費用です。
財源は、介護認定事務費の約50%を国が負担する以外は、全て市が負担します。
保険給付費用の財源
介護保険では、保険を利用した人と利用しない人との負担の公平上、介護サービスにかかる費用の1割が利用者負担となっています。(平成27年8月から、一定以上の所得がある人は自己負担が2割になります)
残りの9割が介護保険給付費となり、その内訳として公費50%、残りの50%は40歳以上の人が負担します。
40歳以上の人の負担割合は、次のようになっています。
保険給付に要する費用の財源構成
- 65歳以上の人の保険料(22%)
- 市町村毎に保険料額が異なります。
- 市へ納付(年金から天引きまたは直接納付)します。
- 40歳以上65歳未満の人の保険料(28%)
- 医療保険者(健康保険組合や国民健康保険など)が医療保険として保険料を徴収するわけですが、半額は事業主負担です。
- 事業主が集めた保険料は医療保険者へ納付され、最終的には社会保険診療報酬支払基金(全国)へ集められ、そこから各市町村の給付実績の32%分が交付されます。
- 保険料率や納付時期は、医療保険の組合ごとに異なります。
- 市負担(市民の皆さんの税金などで負担します)(12.5%)
- 県負担(税金などで負担します)(12.5%)
- 国負担(約25%)
- 国は全国の市町村の25%分を負担しますが、その内の5%分は調整交付で、交付される側の市町村では5%が次の理由により調整され、3%〜10%位になります。
- (注意1)後期高齢者補正
75歳以上の高齢者が多いと認定者が多くなり、給付費も増となりますので、全国平均との調整をします。 - (注意2)所得補正
保険料の段階別人数に極端に差があると、保険料の改正額や実際の徴収額にも影響しますので、全国平均との調整をします。
このように皆さんの保険料は、保険給付費だけに充てられ、他の事務的経費には一切充てることができない明朗な会計となっています。
すなわち、国民全員で費用を負担しあいながら、社会全体で支え合っているのが介護保険です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 介護高齢福祉係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
お問い合わせフォームはこちら
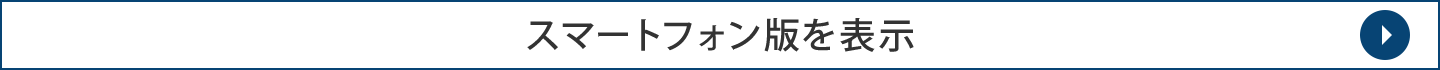








 総合トップ
総合トップ 組織から探す
組織から探す 相談窓口
相談窓口 お問い合わせ
お問い合わせ 行政サイト
行政サイト 移住定住サイト
移住定住サイト 子育てサイト
子育てサイト 観光協会
観光協会
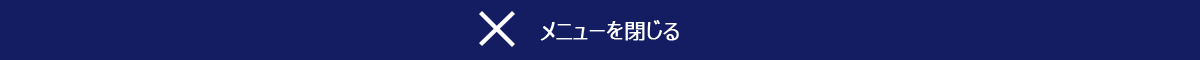

更新日:2019年08月01日